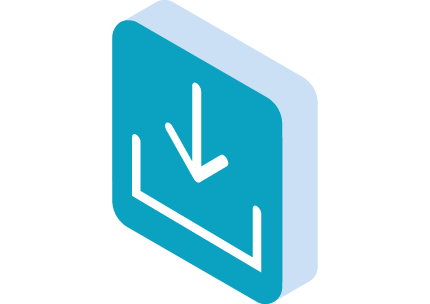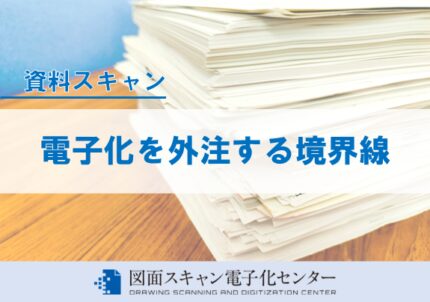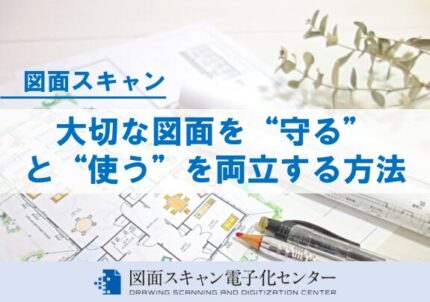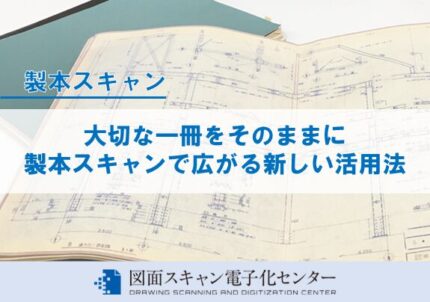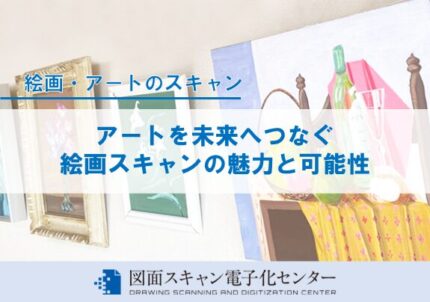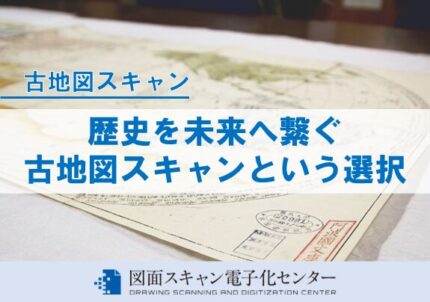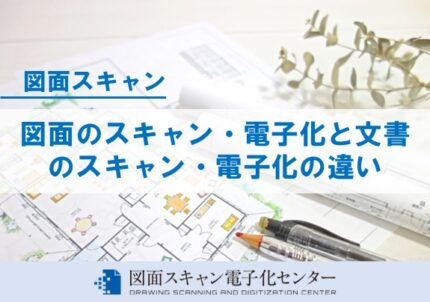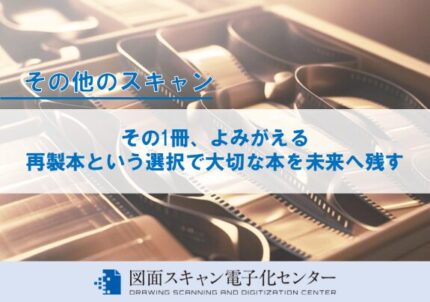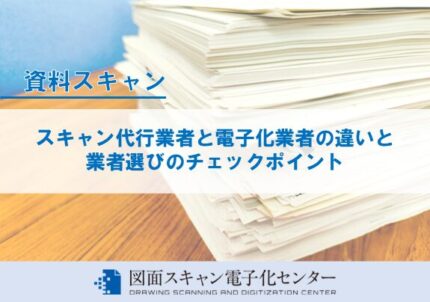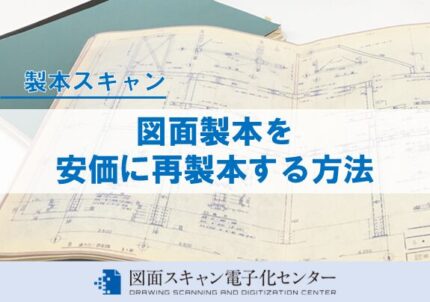● OCRとは? 文字を読み取りデジタル化する技術
OCR(Optical Character Recognition)は、紙に印刷または手書きされた文字を、スキャナーやスマートフォンで読み取り、コンピュータ上で扱えるテキストデータに変換する技術です。
たとえば、過去の契約書、FAXで届いた注文書、手書きのアンケート用紙など、アナログ情報をデジタル化する際にOCRは非常に有効です。
画像として取り込んだだけでは「見られる」だけのデータですが、OCRを通すことで「検索」「コピー」「編集」できる“使える情報”に変わります。
これにより、情報の利活用の幅が一気に広がります。
紙資料が多く残る業務フローの中で、OCRは“情報を眠らせない”ための強力なツールです。

● 手入力からの解放と業務の効率化
紙の資料を扱う際、従来は人の手によってひとつひとつデータ入力する必要がありました。
OCRはこの工程を自動化することで、大幅な時短と人的ミスの削減を実現します。
定型帳票や申請書、名簿などに特に効果を発揮し、数百件単位の処理でも安定した精度で対応可能です。
また、OCRによる読み取り結果はCSVやExcel形式で出力できるため、他の業務システムとの連携も容易です。
スタッフの入力作業を減らし、「判断」や「分析」といった本来の業務に集中できる環境づくりにも繋がります。

● 検索性が高まり、情報資産が活きる
OCR化されたデータは、単に文字として残るだけでなく、“検索可能な情報”として機能します。
「○○という名前の書類」「◯月の資料に出ていたキーワード」などをすぐに検索できるため、紙資料では時間がかかっていた確認作業が一瞬で完結します。
これはアーカイブ業務やバックオフィスの書類管理において、圧倒的な生産性向上をもたらします。
さらに、OCRで得られたテキストをデータベースに蓄積すれば、検索や集計、レポート作成の自動化も可能になります。
「見つけられること」は、「活かせること」に繋がる——OCRの真価は、まさにそこにあります。

● 精度の向上とAIによる補完技術
かつてのOCRは「活字だけしか読めない」「誤認識が多い」といった弱点がありました。
しかし、近年はAIとの連携により、手書き文字や表組み、非定型レイアウトへの対応力が飛躍的に向上しています。
たとえば、書類のレイアウトを自動解析して項目ごとに抽出したり、かすれた文字やクセ字でも補完しながら正確に変換する「AI-OCR」が広がっています。
また、複数言語対応や自動翻訳との連携も可能で、グローバル対応や多様な業務でも応用が利くようになりました。
OCRは今や、単なる“読み取り技術”から“業務理解型AI”へと進化しているのです。
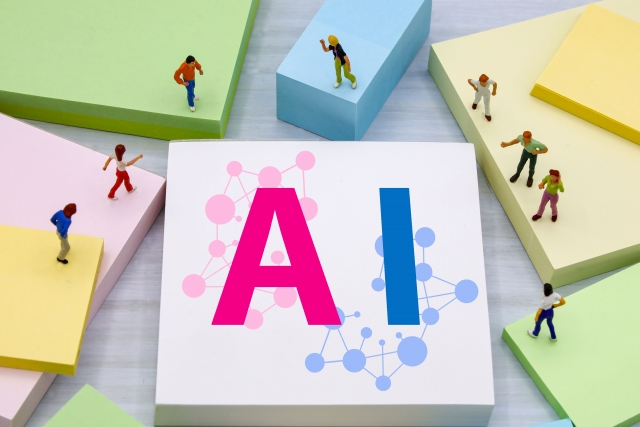
● OCRは導入から運用までがカギ
OCRは強力な技術ですが、成果を最大化するためには「使い方の設計」が重要です。
まず、「何を読み取り」「どう活用するか」という目的を明確にすることが成功の鍵となります。
データ出力後の形式、保存ルール、アクセス管理など、業務フローに合った仕組みを整えることで、定着率が高まり、効果も安定します。
最近は、クラウド型OCRやRPA(業務自動化)との連携により、OCR処理からシステム登録までを完全自動化する事例も増えています。
単なる作業の一部ではなく、「働き方そのものを変える」ための仕組みとして導入する視点が求められています。